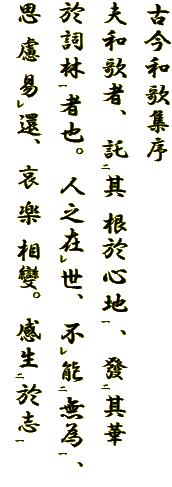真名序原文(全文)-1
|
真名序詠み下し(送り仮名は平仮名で表記) 現代語訳(解釈)へ
|
夫和歌者、託其根於心地、発其華於詞林者也。
人之在世、不能無為、思慮易遷、哀楽相変。感生於志、詠形於言。
是以逸者其声楽、怨者其吟悲。可以述懐、可以発憤。
動天地、感鬼神、化人倫、和夫婦、莫宜於和歌。
和歌有六義。一曰風、二曰賦、三曰比、四曰興、五曰雅、六曰頌。
若夫春鶯之囀花中、秋蝉之吟樹上、雖無曲折、各発歌謡。
物皆有之、自然之理也
然而神世七代、時質人淳、情欲無分、和歌未作。
逮于素戔烏尊、到出雲国、始有三十一字之詠。
今反歌之作也。其後雖天神之孫、海童之女、莫不以和歌通情者。
|
やまとうた あづ あば
それ和歌は、その根を心地に託け、その花を詞林に発くものなり。
あた うつ あひ きもち な
人の世にある、無為なること能はず、思慮遷り易く、哀楽相変る。感は志に生り、詠は言に形る。
ここ もっ
是を以て、逸する者はその声楽しく、怨ずる者はその吟悲し。以て懐を述べつべく、以て憤を発しつべし。
あめつち
天地を動かし、鬼神を感ぜしめ、人倫を化し、夫婦を和ぐること、和歌より宜しきはなし。
りくぎ いは
和歌に六義あり。一に曰く・風、二に曰く・賦、三に曰く・比、四に曰く・興、五に曰く・雅、六に曰く・頌
さへづ うた
かの春の鶯の花中に囀り、秋の蝉の樹上に吟ふがごとき、曲折なしといへども、各歌謡を発す。
ことわり
物皆これあり、自然の理なり。
あつ おこ
然れども、神の世七代は、時質に人淳うして、情欲分かつことなく、和歌未だ作らず。
すさのをのみこと およ み そ ひ と も じ
素戔鳴尊の出雲の国に到るに逮びて、始めて三十一字の詠あり。
かへしうた おこり むすめ
今の反歌の作なり。その後天神 の孫、海童の女といえども、和歌をもちて情を通ぜずといふことなし。
|
真名序原文(全文)-2 |
真名序詠み下し(送り仮名は平仮名で表記) 現代語訳(解釈)へ |
爰及人代、此風大興、長歌短歌旋頭混本之類、雑躰非一、源流漸繁。
譬猶払雲之樹、生自寸苗之煙、浮天之波、起於一滴之露。
至如難波津之什献天皇、富緒川之篇報太子、或事関神異、或興入幽玄。
但見上古歌、多存古質之語、未為耳目之翫、徒為教戒之端。
古天子、毎良辰美景、詔侍臣預宴筵者献和歌。
君臣之情、由斯可見、賢愚之性、於是相分。
所以隋民之欲、択士之才也。
|
ここ
爰に人の代に及びて、この風大きに興る。長歌・短歌・旋頭・混本の類、雑体一にあらず、源流漸く繁し。
たと
譬へば、なほ、雲を払ひし樹の寸苗の煙より生り、天を浮べし波の一滴の露より起るがごとし。
じゅう たてまつ へん
難波津の什を天皇に献り、富緒川の篇を太子に報へしが如きに至りては、或いは事神異に関り、或いは興幽玄に入る。
がん
但し、上古の歌を見るに、多くの古質の語を存し、いまだ耳目の翫とせず、徒に、教戒の端とせり。
いにしへ りゃうしん じしん うたげのむしろ
古の天子、良辰美景ごとに、侍臣の宴筵に預かる者に詔して和歌を献らしむ。
くんしん こころ けんぐ さが
君臣の情、これによりて見るべく、賢愚の性、ここにおきて相分る。
ねが したが ゆえん
民の欲ひに隋ひて、士の才を択ぶ所以なり。
|
真名序原文(全文)-3 |
真名序詠み下し(送り仮名は平仮名で表記) 現代語訳(解釈)へ |
自大津皇子之初作詩賦、詞人才子慕風継塵、移彼漢家之字、化我日或之俗。民業一改、和歌漸衰。
然猶有先師柿本大夫者、高振神妙之思、独歩古今之間。
有山辺赤人者、並和歌仙也。其余業和歌者、綿々不絶。
及彼時変澆漓、人貴奢淫、浮詞雲興、艶流泉涌、其実皆落、其華孤栄、
至有好色之家、以此為花鳥之使、乞食之客、以此為活計之謀。
故半為婦人之右、雖進大夫之前。
近代、存古風者、纜二三人。然長短不同、論以可弁。
華山僧正、尤得歌躰。然其詞華而少実。如図画好女、徒動人情。
|
おおつのおうじ
大津皇子の初めて詩賦を作りしより、詞人、才子風を慕ひ塵に継ぎ、かの漢家の字を移して、我が日域の俗を化す。民の業一たび改りて、和歌 漸く衰へぬ。
然れども、なほ先師柿本大夫という者あり、高く神妙の思ひを振りて古今の間に独歩せり。
山辺赤人といふ者あり、ともに和歌の仙なり。その余の和歌を業とする者、綿々として絶えず。
げうり しゃいん
かの時は澆漓に変じ、人は奢淫を貴ぶに及びて、浮詞雲のごとく興り、艶流泉のごとく涌き、その実皆落ち、その花ひとり栄えて、
いろごのみ これ もち こじき かっけい はかりごと
好色の家に有りては、此を以て花鳥の使とし、乞食の客は此を以て活計の謀となすに至る。
だいぶ
故に、半ば婦人の右となし、大夫の前に進めがたし。
わづ
近き代に、古風を存する者は纜かに二三人なり。然れども、長短同じからず、
わきま
論じて以て弁ふべし。
かざんそうじょう
花山僧正は、尤も歌の体を得たり。然れども、その詞、花にして実すくなし。図画好女の徒らに人の情を動かすがごとし。
|
真名序原文(全文)-4 |
真名序詠み下し(送り仮名は平仮名で表記) 現代語訳(解釈)へ |
在原中将之歌、其情有余、其詞不足。如萎花雖少彩色、而有薫香。
文琳巧詠物。然其躰近俗。如賈人之着鮮衣。
宇治山僧喜撰、其詞華麗、而首尾停滞。如望秋月遇暁雲。
小野小町之歌、古衣通姫之流也。然艶而無気力。如病婦之着花粉。
大友黒主之歌、古猿丸大夫之次也。頗有逸興、而躰甚鄙。
如田夫之息花前也。
此外氏姓流聞者、不可勝数。其大底皆以艶為基、不知和歌之趣者也。
俗人争事栄利、不用詠和歌。悲哉々々。
雖貴兼相将富余金銭、而骨未腐於土中、名先滅世上。
適為後世被知者、唯和歌之人而巳。何者、語近人耳、義慣神明也。
|
こころ すぼ
在原の中将の歌は、その情余りありて、その詞足らず。萎める花の 彩色少なしといへども、薫香あるがごとし。
てい こじん
文琳は巧みに物を詠ず。然れども、その体俗に近し。賈人の鮮かなる衣を着たるがごとし。
宇治山の僧喜撰は、その詞は華麗にして、首尾停滞せり。秋の月を望むに、暁の雲に遇へるがごとし。
おののこまち いにしえ そとおりひめ
小野小町が歌は、古の衣通姫の流なり。然れども艶にして気力なし。病める婦の花粉を着けたるがごとし。
おおとものくろぬし さるまるだゆう すこぶ いっきょう ひな
大友黒主が歌は、古の猿丸大夫の次なり。頗る逸興ありて、体甚だ鄙し。
でんぷ やす
田夫の花の前に息めるがごとし。
この外に氏姓流れ聞ゆる者、あげて数ふべからず。その大底は皆艶をもちて基をなし、和歌の趣きを知らざる者なり。
俗人争でか栄利を事として、和歌を詠ずることを用いざる。悲しきかな悲しきかな。
貴きこと相将を兼ね富は金銭を余せりといへども、骨いまだ土中に腐ちざるにして、名まづ世上に滅えぬ。
適後世になすを知らるる者は、唯和歌の人のみ。いかにとなれば、語は人の耳に近く、義は神明に慣へばなり。
|
真名序原文(全文)-5 |
真名序詠み下し(送り仮名は平仮名で表記) 現代語訳(解釈)へ |
昔平城天子、詔侍臣令撰万葉集。
自爾来、時歴十代、数過百年。其後、和歌弃不被採。
雖風流如野宰相、軽情如在納言、而皆以他才聞、不以漸道顕。
陛下御宇于今九載。仁流秋津洲之外、恵茂筑波山之陰。
淵変為瀬之声、寂々閇口、砂長為巌之頌、洋々満耳。
思継既絶之風、欲興久廃之道。
爰詔大内記紀友則、御書所預紀貫之、前甲斐少目凡河内躬恒、
右衛門府生壬生忠峯等、各献家集、并古来旧歌、曰続万葉集。
於是重有詔、部類所奉之歌、勒為二十巻、名曰古今和歌集。
臣等、詞少春花之艶、名竊秋夜之長。
況哉、進恐時俗之嘲、退慙才芸之拙。
適遇和歌之中興、以楽吾道 之再昌。嗟乎、人丸既没、和歌不在斯哉。
于時延喜五年歳次乙丑四月十五日、臣貫之等謹序。
|
へいぜい みことのり えら
昔、平城の天子、侍臣に詔して万葉集を撰ばしむ。
それ以来、時は十代を歴、数は百年を過ぎたり。その後、和歌棄てて採られず。
風流、野宰相の如く、軽情、在納言の如しといへども、皆、他の才をもちて聞え、この道をもちて顕はれず。
ぎょ う
陛下(醍醐天皇)の御宇今に九載なり。仁は秋津洲の外に流れ、恵は筑波山の陰よりも茂し。
じゃくじゃく いはほ しょう
淵の変て瀬となすの声、寂々として口を閉ぢ、砂の長じて巌となすの頌、洋々として耳に満てり。
既に絶えし風を継がむと思ひて、久しく廃れし道を興さむと欲っす。
ここ だいないき きのとものり ごしょのところのあずかり きのつらゆき さき しょうさかん おほしかふちのみつね
爰に、大内記の紀友則・御書所預の紀貫之・前の甲斐の少目凡河内躬恒、
えもんのふしょう みぶのただみねら
右衛門府生の壬生忠岑等に詔して、各に家の集、ならびに古来の旧歌を献らしめ、続万葉集といふ。
ろく
ここにおいて、重ねて詔あり、奉るところの歌を部類し、勒して二十巻とし、名づけて古今和歌集といふ。
ぬす
臣等、詞は春の花の艶少きに、名は秋の夜の長きを竊めり。
あざけり つたな は
況むや、進みては時俗の嘲を恐れ、退きては才芸の拙きを慙づるを。
さか ああ
適和歌の中興に遇ひて、もちて吾が道の再び昌りなることを楽しぶ。嗟乎、人丸既に没して、和歌ここにあらずや。
えんぎ きのとうし
時に延喜五年、歳次は乙丑四月十五日、臣貫之等 謹みて序す。
ページ
|
古今和歌集真名序・現代語訳-1 |
文中語句解説 戻る真名序詠み下しへ |
さて和歌というものは、その根を心の状態に託して、その花を文人社会に発表するものである。
人の世にある無作為なるが事を成し得ず、思いめぐらした考えは移り変り易く、悲しみと楽しみは何時でも入れ替わり得る。感情は心の向かうところとなって、詠嘆は言葉を形作る。(形る=語る)
こう云う訳で、気ままにふるまう者はその声も楽しく、恨み言を云う者はその吟詠も悲しい。よって胸中を語るのがよく、よって憤りを発散してしまうのが良い。
天つ神と国つ神を動かし、鬼神(勢い荒ぶる神々)を感動させて、人道を徳を以って導き、夫婦を仲睦まじくさせる事、和歌よりふさわしいものはない。
和歌に六義(漢詩の六義に基づいた六種の体)が有る。
一つ目に云う事には「風(ふう=添え歌)」、
二つ目に云う事には「賦(ふ=数え歌)」、
三つ目に云う事には「比(ひ=なぞらへ歌)」、
四つ目に云う事には「興(きょう=たとえ歌)」、
五つ目に云う事には「雅(が=ただごと歌)」、
六つ目に云う事には「頌(しょう=祝い歌)」である。
あの春の鶯の梅の花の中での囀り、秋の蝉の樹上で唄っているかのような様は、毎年の事だから変り映えなしとは言っても、それぞれ韻律を発しているようである。物には皆これが有る、自然の道理である。
おもい
然しながら、神の世七代では、時間も質も人の情け厚くして、様々な欲求の情の分けられることなく、和歌は未だに復興していない。
素戔鳴尊が出雲の国に行き着いたことで漸く最初の三十一文字の歌が詠われた。今の返歌の起こりである。その後天神の孫、海童の娘と雖も和歌でもって情を通わせていないなどという事は無い。
|
夫;漢文の「夫」の訓読。改まった気持ちで文を起こし、又は物事を述べ立てるのに用いる。
あまつかみ
天つ神;高天原(天上の国)の神。古事記では天御中主神など。
くにつかみ
国つ神;国土を支配し守護する神。地神・地祇とも書く。
りょうのぎげ おおみわ おおやまと かつらぎ やましろのくにのかも いずものおおなむちのかみ
令義解では大神・大倭・葛木・山城国鴨・出雲大汝神を挙げる。
おにがみ
鬼神;猛々しく恐ろしい神。
きじん
鬼神;死者の霊魂と天地の神霊として、人の耳目では接することの出来ない超人的な能力を有する存在。
はんか
返歌;神々や英雄の伝説などを客観的に表現した長歌の後に添えられた短歌を特に反歌(はんか)と呼びならわす。解釈の意を込めた要約・補足の歌。
すさのおのみこと いざなぎのみこと あまてらすおおみかみ
素戔鳴尊;日本神話で伊弉諾尊の子で天照大御神の弟。凶暴で高天原へ行って天の岩屋戸の事件を起こし、諸神によって高天原から追放されて、出雲の国へ出向き八岐大蛇を切り退治した後、天叢雲剣(後の草薙の剣)を得て天照大御神にこれを献上して、根の国(黄泉の国)へ赴いた。
|
古今和歌集真名序・現代語訳-2 |
文中語句解説 戻る真名序詠み下しへ |
ここに人の世に及んでこの風大いに起こる。長歌・短歌・旋頭歌・混本歌の類、雑体も一つではない。起源はおもむろに賑わって来出した。
例えば、あたかも雲を払うかのような大樹の小さな早苗の煙より生じて、大空を浮べる波(大海原の波)も一滴の露(雫)から始まるのに似ている。
難波津の詩編を天皇に献上して、富緒川の詩篇を皇太子に報いるかのような態度に至っては、或は事は人知を越えた神秘霊妙に関わり、或は興は幽玄に入ることになる。
但し、かなり昔の歌を見ると多くの古い体質の語句が存在し、未だに耳目のおもちゃとならず、いたずらに教戒(教え戒める事)の糸口としてしまっている。
昔の天皇は吉日や美しい景色ごとに、侍臣(君子の傍に仕える役人)の宴の席にいる幹事に御言宣(命令)をして和歌を献上させた。
君子と臣下それぞれの心の内をこれに依って当然見るはずであり、賢者か愚者かの持って生まれた性質は、この事(宴の関での和歌の即興)に於いてお互いに理解しあうのである。
民の願いに応じて仕官の才能を選ぶ理由である。
|
せどうか
旋頭歌;下三句が頭三句と同じ形式を反復する所から云う和歌の一体。五七七・五七七の片歌を反復した六句体。唱歌に起源があると云われ、本来民謡的な歌いものが多く、上代の物が多い。
こんぽんか
混本歌;和歌の一体であるが、何を指しているのかは未だに定説がない。
甲、旋頭歌又は同様の体ではないかと見る、六句体歌説
乙、俳句と和歌の間ではないかと見る、四句体説。
丙、片歌又は五・七音の対の幾つかが連続する偶数形式の歌ではとする説。
難波津の詩篇;手習の初めに学ぶ歌「難波津に咲くやこの花冬ごもり、今は春辺と咲くやこの花」
きょう
興;草木鳥獣などに託して比喩を表すこと。
ゆうげん
幽玄;奥が深く微妙で味わい深く情緒に富んだ境地。
じもく の おもちゃ
耳目の玩具;見たまま、聞いたままを自由に使いこなすこと。
|
古今和歌集真名序・現代語訳-3 |
文中語句解説 戻る真名序詠み下しへ |
大津皇子の初めて詩賦を作った時より、文人、才子は風を慕い、世俗の煩わしさを繋いで、かの中国漢朝の漢字を移して我が天下の世俗を教え導く。
人々の行動は一気に改まって、和歌は段々と衰えてしまった。
然しながら、なお先代の師匠である柿本人丸先生が居られて、多いに大変優れた技の心を呼び覚まして、昔から今に至るまで他に類なく優れた様子である。
山部赤人と云う者は共に並んで和歌の才能の優れた人である(歌仙)。
その他の和歌を生業とする者長く続いて絶えることがない。
かの時は世も末となって道徳が衰え、人情も薄くに転じて、人は贅沢におごり、度を越して浸ることに価値が有ると思うに至って、浮いた言葉が雲の様に沸き上がり、妖艶美や風流な詞が泉のように次々と湧き出て、その実(身)は全て落ち、その花は独り栄えて、色好みの家に在っては、これを以って花鳥の使いとし、托鉢の客はこれを以って生活の計の心算と為せるに至る。ゆえに、半ば婦人の右側となり太夫(人丸)の前には進め難いのである。
近代に古風を心得ている者は僅かに二・三人である。然しながら、長短同じではない、議論することによってわきまえるべきである。
花山僧正は、尤も歌の有様を表現している。然しながら、その言葉は華やかではあるが、実が少ない。絵に描いた美女を見て無駄に人の情を動かすのと同じようである。
|
おおつのおうじ
大津皇子;天武天皇の王子で歌人。文武に長じ、その詩は当代有数とされて「懐風藻」に4首収まる。歌も万葉集中でも異色で、草壁皇子(異母)と共に皇位継承の有力候補であったため天武天皇の崩御後、草壁皇子の母である持統天皇によって謀反の名目で処刑された。(生年663年~没年686年)
くわいふうさう
懐風藻;現存最古の漢詩集。天平勝宝三年(751年)の序が有る。天智天皇時代から奈良時代に至る六十四人の詩120編を年代順に集めた物で、六朝の詩風に倣った日本古詩の精髄を伝える。
文人;文事に携わる人。詩文・書画などの文雅なことに従事する人。
才子;知才の優れた人。
「その実(身)は全て落ち、その花は独り栄えて」
真実味が薄れて中身のないこととなり、詩文のみが見栄えて、
ふげん
浮言;根拠のない噂。根も葉もないのない風説。
はかりごと
謀;心づもり。前もって考えた計画。もくろみ。
古風;昔ながらの習慣や流儀。特に古詩。
|
古今和歌集真名序・現代語訳-4 |
文中語句解説 戻る真名序詠み下しへ |
在原の中将(在原業平)の歌は感情が豊か過ぎて言葉に言い尽くせず。
萎んでしまった花の色艶こそ少なくなったと云っても、良い香りが備わっているかのように。
文壇の仲間たちは巧みに物を詠ずる。然しながらその有様は風流ではなくありふれたものに近い。商人の見栄えのする鮮やかな衣服を身に着けるかのように。
宇治山の僧、喜撰はその言葉は華麗ではあるものの、終始停滞している。
秋の月を眺めようとしているのに、それが実現しようとするその時に雲に出くわすかのように。
小野小町の歌は古の衣通姫の流れを汲むものである。然しながら、麗しく輝くようではあっても力強さに欠ける。青白い顔の婦人が花粉で化粧をするかのように。
大友黒主の歌は、古の猿丸大夫の次である。いささかではあるが一寸した面白味があって、一見のありさまは甚だ都を離れた田舎のようだ。風流味の分からない武骨な人が花の前で一休みしているかのようなものである。
この他に、氏・姓・家系のよく知られている者たちを、拾い上げて数えてはならない。その大本はほぼ全て優雅で魅力的な美を好むことを基本として、和歌の趣を知らない者たちである。
俗人は張り合ってか栄誉と利益を得ることに熱中して、和歌を詠むことを利用してはいけない。返す返すも痛々しいものである!。
貴き事それは、宰相と将軍を兼ねて富(財産)として金銭を有り余るほど残したとしても、骨が未だ土に還らない内にその名が世の中から消えてなくなることである。
心に叶うこと、後世にその名を知られる者は唯一和歌の人だけである。どうしてかと云えば、語りは人の耳に近く、物事の道理は神明の習慣に従っていればよいのです。
|
在原業平;平安初期の歌人で六歌仙・三十六歌仙の一人。兄の行平らと共に826年に在原姓を賜る。阿保親王の第五皇子で容姿端麗であったことから「伊勢物語」の主人公と混同され、情熱的な和歌の名手として「色男」として扱われ能や歌舞伎・浄瑠璃の題材ともなった。通称在五中将とも云われ官位は蔵人頭、従四位に至る。二条后との密通、それが為の東下り、又伊勢斎宮との密通など。家集に業平集がある。
喜撰;平安初期、弘仁年間の頃に活躍の歌人で六歌仙の一人。山城の国乙訓郡の生まれで、出家して醍醐山に入り、後に宇治山に隠居して仙人になったと伝わる。喜撰法師。確かな歌は『我が庵は都のたつみしかぞ住む、世をうぢ山と人はいふなり』の一首のみ。
うじ
氏;古代、氏族に擬制しながら祭祀、居住地、官職などを通じて結合した政治的集団。姓を異にする家族群に分かれ、上級の姓を持つ家族群が下級の姓の家族群を支配し、最下層には部民及び奴婢が居た。
かばね
姓;古代豪族が政治的・社会的地位を示すため、世襲した称号。初めは私的尊称であったが、大和朝廷の支配が強化されるのに伴って朝廷が与奪するようになり、臣・連が最高の姓となった。大化改新(645)の後、684年に天武天皇が皇室を中心に八色の姓を定め永らく続いたが、やがて姓を世襲する氏よりも氏が分裂した結果である家で政治的地位が分かれる事となり、姓は自然消滅していった。
言葉は世間でよく耳にするし、俗世間の様々なことの正義は天地の神霊や祖先の霊魂を祀る習慣に従っておけば良い。
|
古今和歌集真名序・現代語訳-5 |
文中語句解説 戻る真名序詠み下しへ |
昔、平城天皇が、傍に仕える賢者に詔して万葉集を撰ばせた。
以来より、十の世代の歴史が刻まれて年は百年を過ぎてしまった。その後、和歌は気に留められることも無く採用されなかった。
風流は田舎大臣の有様で、軽んじられた感情はまるで地方の大・中・少納言と云ったところである、とは言え皆それぞれの才能を持って有名であり、和歌の道(世界)としてでは表舞台に現れなかったのである。
陛下(醍醐天皇)の納め給う御代は即位以来九年になられる。
陛下の慈しみの心は秋津洲の外まで行き渡り、その恩恵は筑波山の庇護よりも度重なるほどの量となられる。
淵の変化して(思いもよらぬ時に)瀬となってしまうなどの声、ひっそりとして口を閉じ、砂(細れ石)の成長して巌(大きな岩)ともなると云う褒め歌の数々が、水流の満ち溢れんばかりに耳に届いておりまする。
既に途絶えてしまった習わしを継いでゆこうと試みまして、永い間廃れてしまっておりました歌の道を再興してみようと思うのですよ。
さてここに、大内記の紀友則・御書所預の紀貫之・前の甲斐の少目凡河内躬恒・右衛門府生の壬生忠岑等に詔して、各々にそれぞれの家集、並びに昔から今までの古歌を献上させて続万葉集と名付けた。
ここに来て再び詔が有り、奉るべき歌を部類し整理して二十巻としてまとめたものを名付けて古今和歌集と云う。
朝廷に仕える人々、その言葉は春の花の色艶少なくして、その名は秋の夜の長さを(利用して)秘かに学ぶ。
云う迄もなく、進み出てはその時代の風俗に謗り笑われることを恐れ、退いてしまっては才能と技芸の能力不足を恥じてしまうことを(恐れてのことである)。
願わくば一度衰えた和歌の再興に巡り合って、以て我が道の再び栄える事を快く味わいたいものだ。ああ!人丸(人麻呂)はすでに亡くなっており、彼の和歌(の精神)はここに存在しないのであろうか。(否そんなことは無い、存在しているとも)
記載の日時、延喜五年、歳次は乙丑の四月十五日、撰任者貫之ら謹んで序文を書く。
|
へいぜいてんのう あ て
平城天皇;平安初期の天皇。桓武天皇の第一皇子で名は安殿、奈良帝とも云われる。在位は4年に満たず(806年~809年)、病によって嵯峨天皇に譲位し、旧都である平城京に移った。ここに京都の平安京と奈良の平城京との二ヶ所の朝廷が出来る事となり、侍従による対立が起こるようになる。生年774年~没年824年。
みことのり
詔;勅よりも大事に云う臨時の命令。御言宣の意=天皇のお言葉。
風流;前代の遺風。聖人が後世に残し伝えた良い流儀。
又、風流韻事(風流な趣のある遊びで、自然を楽しみ、詩歌を作って楽しむこと)
田舎大臣;田舎大尽のこと。田舎の財産持ちで、大尽遊びなど豪遊する人。
あ き づ し ま
秋津洲;大和の国。日本国のこと。秋津島・蜻蛉洲とも書く。
だいないき・ きのとものり
大内記・紀友則、正六位上。
ごしょのところのあづかり・きのつらゆき
御書所預・紀貫之、従八位上。
さきのかいのしょうさかん・ おほしかふちのみつね
前甲斐少目・凡河内躬恒、従八位下。
えもんのふしょう みぶのただみね
右衛門府生・壬生忠岑、従八位下。
風俗;世間の習わし。風習。しきたり。
ちゅうこう
中興;一旦衰えてしまったものを再び興すこと。
さいじ
歳次;「歳」は木星、「次」は宿りの意。古代中国で二十八宿(一ケ月)を十二次に分け木星は一年に一次を周り十二年で軌道を一周すると云うのに基づく「としまわり」
きのとうし
乙丑;十干と十二支の組合せ。60通りの組合せが有り、紀年法に用いる。60年に一度元に戻る(還暦)。
|